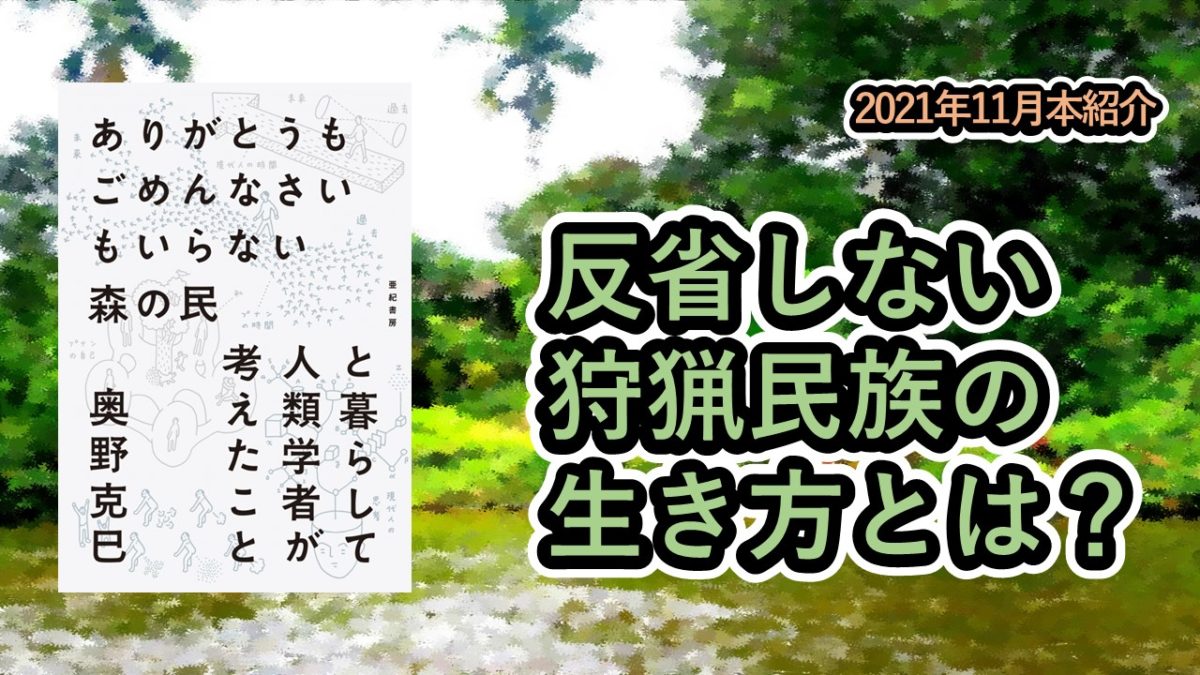記事 /
【本を読もう!】『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』奥野克己【2021年11月本紹介】
- #お役立ち
こんにちは!シンダイガイドのはるかです!本紹介シリーズ第2弾。今回は奥野克己さんの『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』という本を紹介します!
本紹介シリーズは、毎月ライターの独断と偏見でセレクトした、信大生に読んで欲しい本を紹介していきます!また後半では生協フェア情報、図書館の新刊情報があります。こちらも是非チェックしてください!
大学生の半数が本を読まないと言われています。この記事をきっかけに、1冊でも本を読んでくれたら嬉しいです。
今月のオススメ本紹介
ボルネオの狩猟民族「プナン」
ライター(私)は用がなくても本屋さんをふらふらするのが好きです。この本はそんなときに見つけた本です。
『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』というタイトルをみてライターは衝撃を受けました。
日本では当たり前の「ありがとう」と「ごめんなさい」。それを使わないでどうやって暮らしているのか。とても気になりました。
この本で紹介されているのは「プナン」というボルネオの森で暮らしている狩猟民族です。彼らは森に生息しているヒゲイノシシなどを食料として暮らしています。
それだけでも日本に住む私たちには想像できないことですが、プナンと日本人との違いはその生活様式だけではありません。価値観、文化がまるで違います。
この本には筆者が体験し驚いたさまざまな価値観や文化の違いが書かれていますが、その中でも私が特に印象に残ったものを紹介したいと思います。
反省しない民
プナンは反省をしません。プナンは過失に対して謝罪もしなければ反省もしないのだと奥野さんはいいます。プナンが反省しないことが分かる、著者の奥野さんが実際に経験したエピソードを紹介します。
奥野さんが町で買って持ち込んだバイクをプナンの人たちに貸すと、タイヤをパンクさせても何も言わずにそのまま返してきました。バイクのタイヤに空気を入れるポンプを貸すと、木材を運搬するトレーラーに轢かれてぺちゃんこになったまま返却してきたのです。
またある時、共同体のリーダーはプナンの持つ森を伐採した企業からの賠償金を前借して、それを頭金として四輪駆動車を購入しました。その車にプナンのハンターたちを乗せてヒゲイノシシ猟へ連れていきます。
獲れた猪肉を売って得た現金を山分けするとともに、車のローンの支払いに充てようとしました。売上金は共同体の全メンバーに報告されました。しかし老いて狩猟に同行しないリーダーにはいつも売上金の十分の一ほどの金額しか手渡されませんでした。
実はハンターたちが酒を飲むのに使ってしまったのです。リーダーはそのことをうすうす気づいているようでしたが、あえて取り沙汰しませんでした。
結局車のローンも払えなくなり、手に入れた車を手放す羽目になってしまいました。共同体のメンバーでこのことについて話し合われましたが、個々のハンターの責任は追及されることがなく、あまり有効ではないと思われる策が示されただけでした。
反省しないプナン、反省を求める日本
このようにプナンの人たちは反省をしませんし反省を強いることもしません。逆に日本では常に反省することが求められます。
失敗したり悪いことをしたら、謝るのは当然とされています。目標を達成できないと次は達成できるようにと反省を強いられます。というよりも反省を強いられるどころか自ら反省をする人が多いでしょう。
奥野さんは反省をすることによって個人の悩みは深まり生きにくさを感じるようになるのかもしれないと考えました。

精神病がないプナン
面白いことにプナンには精神病がないようです。原始的な暮らしをしている民族といっても精神病がみられる部族も存在します。それでもプナンには精神病がないのです。少なくとも奥野さんは精神病を患っているプナンに会ったことがないそうです。それはもしかしたら反省しない民族性のおかげかもしれません。
私たちは日々反省することで成長しよりよい人生にできると信じています。ですが反省をしすぎて自分を追い込んでしまうと、時にはうつ病になってしまうかもしれません。
プナンの生き方を見ていると反省することが必ずしも良いことではないと思えてきます。少なくとも反省をしなくてもいい生き方があるのだということをプナンは教えてくれます。
みんなで分け合うという生き方
プナンの特性の中でもう一つ面白いと思ったことを紹介します。
奥野さんはプナンの集落へ行くたびにお世話になっている家族へ何かお土産を持っていくそうです。日本製の腕時計やポーチなどを持ってくそうですが、それらはすぐに別の人へ渡ってしまうのです。持って行ったお土産が全く知らないプナン人に渡っていたこともあったそうです。

お土産を受け取ったプナンの人がすぐに他の人にあげてしまうのです。これにはプナン独特の価値観が関係しています。
プナンはねだられたら惜しみなく分け与えるということが期待されています。しかも人によくものをあげる人は尊敬の対象になるので、尊敬されている人ほどみすぼらしい格好をしています。
日本や欧米の国などはお金を持っているほうがうらやましがられ、権威もあります。それとは正反対ですね。
森で生き抜くための知恵
この習慣はプナンの人たちが生まれながらにして持っているものではないようです。その証拠にプナンの小さい子たちはもらった飴を独り占めしようとするのです。それを親たちが他の子どもたちに分け与えるように促します。
人にものを惜しみなくあげる習慣があっても、実はやりたくてやっているわけではないのです。先ほどの奥野さんからお土産をもらったプナンの人もできればお土産を他の人に分けたくないそうです。
それでもこの習慣が根付いているのはなぜか。奥野さんはこの習慣は森の中で生き抜くためにプナンが身につけた知恵だと言います。獲物が十分に取れなくてもみんなで分けて集団全体で生きていこうというわけです。
感想
私が面白いと思ったものについて2つほど紹介しました。プナンという民族のことを初めて知ったので新鮮なことばかりでした。
私たちは普段とても忙しく生きています。大学生なら授業やサークル活動、バイトに追われています。
高校生の頃は勉強で忙しかったことでしょう。大学を卒業したら、多くの人は就職して毎日会社へ行かなければなりません。
それに対してプナンの人たちの生活はゆったりとしたものでした。時間を気にせず狩りで獲物が捕れたら食事をし、また狩りをし、という生活です。正直うらやましいなと感じてしまいます。
生きる意味を考えない
この本のなかで特に印象深かった言葉は「生きるために食べる」ということです。私たちは「生きる意味」を考えがちです。「自分探し」とか「やりたいことを仕事にしよう」みたいな言葉をよく目にします。
ですがプナンたちはそんなことを考えてはいません。ただ毎日生きているだけなのです。現代の日本に住んでいると「生きている」ことの凄さとか、すばらしさを忘れがちです。
プナンの生き方に触れることで「生きている」ことのすばらしさを再確認できたような気がします。「生きる意味」を考えて悩んでしまいがちですが、生きているだけでいいんだと思うとなんだか気持ちが楽になります。
生協フェア情報
「ラダーシリーズ」が全品15%OFF!

現在生協では、英語の多読を学習者のレベルに合わせてできる「ラダーシリーズ」が全品15%OFFとなっています!フェアに合わせて、品揃えも豊富になっています。
大学生になっても英語学習は必須。TOEICをはじめとする英語の試験対策に、英語力の向上を目指しましょう!
多読をすれば読解力の向上や、語彙力の増強を期待できます。
「ラダーシリーズ」はご存じの方も多いと思いますが、学習者のレベルに合わせて難易度を選択できます。それに加えて好きな物語を選べるので楽しく英語学習ができます。
15%OFFで購入できるこの機会に是非多読をはじめて英語力をアップしちゃいましょう!
図書館新刊情報
『『ジョジョの奇妙な冒険』で英語を学ぶッ!』
英語の勉強は大切ですが、大変と感じるときもありますよね。そんな人のために楽しく英語を勉強できる本を紹介します。
この本はご存じ『ジョジョの奇妙な冒険』で英語を学ぶ本です。ジョジョに出てくる名台詞で英語を学習できます。一見ふざけた本に見えるかも知れませんが、音読を繰り返せばちゃんと実力がつきます。
どのページにもマンガの名シーンが掲載されているので、雰囲気を味わいながら英語学習ができます。
英語学習に飽きてきたけどやらなければならない人、ジョジョが好きな人、マンガが好きな人は是非手に取ってみてください。この本を図書館に置いてもらえるなんて嬉しいですねッ!
『最後通牒ゲームの謎 進化心理学からみた行動ゲーム理論入門』
皆さんは「最後通牒ゲーム」をご存じですか?最後通牒ゲームというのはゲーム理論においてよく出てくるゲームの一つです。
AさんとBさんがいたとします。Aさんに1000円渡し、それをBさんと分け合います。Aさんは1000円をどのように分けるか決めることができます。BさんはAさんが分けてくれたものを受け取るか、受け取らないか決めることができます。
もし受け取らないと決めたらAさんもお金を受け取ることができません。この場合あなたがAさん、またはBさんだったらどのようにするでしょうか。
伝統的な経済学の「模範解答」はAさんは999円と1円に分け、Bさんは受け取るという選択をします。この答えを聞いて納得できますか?多くの人は違和感を感じると思います。Aさんなら500円と500円に分ける人が多いと思いますし、Bさんなら自分の取り分が1円だったら受け取らないと答える人が多いのではないでしょうか?
この「模範解答」と、実際の行動の違いについて考えていくのがこの本です。「最後通牒ゲーム」って面白いな、と思った人は、是非読んでみてください!
まとめ
いかがでしたか?今月の図書館の新刊は、英語関連の本が多かった印象です。英語の勉強をしたい人は是非図書館へ足を運んでみてください。
来月もライターのオススメ本を紹介する予定です。お楽しみに!