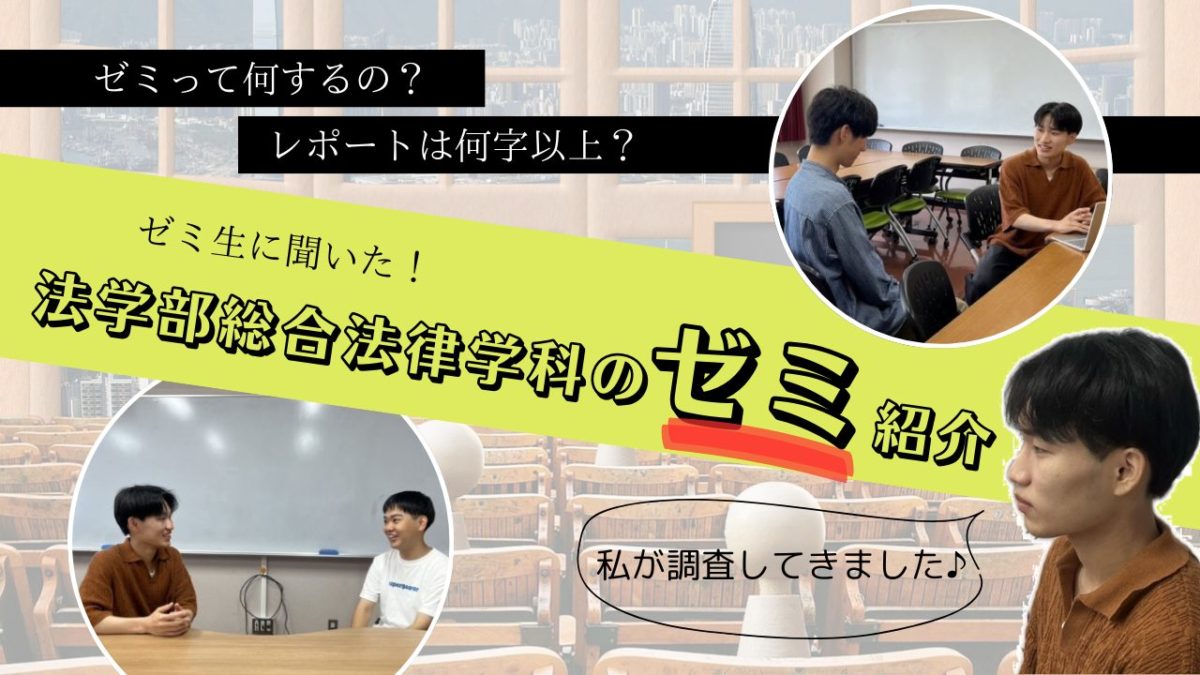記事 /
【ゼミ紹介】ゼミ生に聞いた!経法学部総合法律学科のゼミごとの特徴
- #その他
こんにちは!ライターの〈たか〉です!
総合法律学科のゼミは、1年次の「新入生ゼミナール」、2年次の「基礎演習」、3年次の「発展演習」があります。新入生ゼミナールは元からクラスが割り当てられているのに対し、「基礎演習」「発展演習」は自分で入りたいゼミを選択する必要があります(希望者多数のゼミはGPA等による選考あり)。しかし、詳しい内容は実際にゼミに入ってからしか分かりません。
そこで、今回の記事では2年次の基礎演習における各ゼミの特徴を徹底調査!各ゼミ生に直接インタビューを行い、シラバスや学内の説明会では分からないことも聞いてきました。
法律学科のゼミは何をするの?
法律学科のゼミとは、専門的な法律知識を深めるための少人数のクラスのことです。
刑法や憲法、民法の中の親族・相続法等、ゼミごとに特定の法律分野に焦点を当てて学んでいきます。
グループごとに判例報告(特定の判例について分析し、その概要や争点・問題の所在等についてまとめ、報告を行うこと)を行うゼミもあれば、先生に提示された問題について検討して発表するゼミもあります。また、国際的な問題について検討するゼミもあり、講義内容や進行方法はゼミによって大きく異なるといえます。
ゼミ生にインタビューしてみた!

濱田ゼミ(刑法)
濱田ゼミでは何法について学んでいるんですか?
刑法の総論についてです。総論分野が問題となった判例について、グループごとに判例報告を行います。報告する判例は、一回目の講義で決定します。
講義の日程について教えてください!
1回は顔合わせ、2、3回で発表準備、4~7回で各グループが一回ずつ判例報告、8、9回で発表準備、10~13回で各グループ2回目の判例報告、14回は特別講義、15回はレポート提出用、という感じです。学期中に、1人2回ずつ判例報告を行います。
発表準備の回については、グループごとの自由時間のため、講義室に来る必要はないそうです。
90分の内訳を教えてください!
はじめに、その回の担当グループが30~40分ほど判例報告を行います。判例報告の後は、先生を交えてのディスカッションを行います。先生が概要を説明し、議論点を設定するので、それについて近くの人と考えます。先生がランダムで当ててくるので、当てられたら回答する、という感じです。
30~40分って結構長いですね。レジュメ作成など、発表準備は大変ではないですか?
1グループ5~6人ほどなので、1人1人の負担はそこまで大きいわけではないと思います。発表準備は、1か月くらい前から資料集めを始めて、担当分けをし、レジュメを作り始めます。1週間前くらいに一度集まって読み合せをし、最終調整をするといった感じです。
成績評価はどのように行われるのですか?
判例報告や質疑応答、レポートを総合的に評価されます。レポートは、毎回の判例報告の感想を500字程度でまとめ、最後の週に提出します。
濱田ゼミは2・3年合同で開講されていることも特徴の一つです。
判例報告のグループには3年生が1人以上いるため、わからないことがあった時に頼れる人がいるのは安心ですね!
美甘ゼミ(国際政治)
美甘ゼミは何について学んでいるんですか?
大きな括りでいえば国際政治について学んでいます。色々なテーマについて考えるので、法律要素のないテーマもあります。
法律要素がないというのは特徴的ですね。どのようなテーマについて考えているのですか?
ウクライナ侵攻や日本の社会保障制度、気候変動問題、米中対立など、本当に幅広くです。学生が自分の興味のある問題を先生に伝え、その中から先生がテーマを選びます。
講義はどのように進んでいくのですか?
3週間ごとにテーマが変わります。テーマごとに先生が文献を指定し、その文献について3人グループでまとめます。例えば、1~6章まである文献の場合、1週目は1~3章、2週目は4~6章についてやります。それぞれの週までに、グループ内で1人1章範囲を割り当ててレジュメを作成し、講義時間でグループ内で共有します。その後、問題についての意見をグループごとに発表します。3週目までに、その文献全体について、レポートを作成します。
90分の内訳を教えてください!
はじめに、先生がテーマについて話をします。その後グループで話し合ってまとめる(30分程度)→グループごとに意見を発表する(20~30分程度)、というような流れです。
毎週レジュメ作成やレポート作成があるのは大変ではないですか?
レジュメ作成は文献をまとめる感じなので、すごく大変というわけではないです。レポートは3000字くらいなのですが、提出期限は3週目の次の週なので、時間的にはある程度の余裕はあります。
成績評価は、各テーマごとの3000字程度のレポートや受講態度に加え、後期には5000字の期末レポートが課されるようです。
また、夏季休業中に一度短時間の課外講義があったとのこと。
成澤ゼミ(憲法)

成澤ゼミは何法について学んでいるのですか?
憲法です。使用する教科書に有名判例に即した事例問題があるので、毎回の講義ごとに1つの事例問題を扱います。
事例問題の取り組み方について教えてください!
学期中に、1人1つの事例問題を担当します。事例問題では、重要な論点が1つあるので、それについて回答します。はい又はいいえで答えられる問題なので、すごく厳しいという訳ではないです。
毎回の講義はどのように進んでいくのですか?
はじめに、その回の担当者が10~15分くらいで事例問題の重要な論点について回答します。その後20分くらい先生が解説をし、質疑応答に移ります。その後はまた先生が話します。
先生めちゃめちゃ話しますね!
めちゃめちゃ話します。それもあってか、憲法の知識はすごい頭に入ってます。
成績評価はどのように決まるのですか?
レポートとかはないので、自身の担当する事例問題の発表や質疑応答で評価されてると思います。「良い質問だね」と言われることもあるので、そこは加点要素になっているかもしれません。
総合法律学科では2年次の必修科目に「憲法」がありますが、「憲法」の講義内で重要とされる判例の多くはゼミでも扱っているため、大きなアドバンテージがあるそうです。
また、2年後期からの選択科目である「統治機構論」の先生は成澤先生のため、ゼミ生は悪い成績はつきにくいかも、、?
宗村ゼミ(親族・相続法)
宗村ゼミは何法について学んでいるのですか?
民法の親族・相続法について学んでいます。
講義内容について教えてください!
先生から提示された問題について考えたり、家族法の課題について概要を説明をしたりします。後期には判例演習も行います。
先生からはどのような形式で問題が提示されるのですか?
先生からは択一問題や事案についての問題が出題されます。どちらも最初は個人で検討して、その後グループで話し合い、グループごとに発表するという流れです。グループは、先生があみだくじで3つのグループに分けます。
あみだくじでのグループ分け面白いですね!90分の内訳はどんな感じですか?
択一問題の場合は、あらかじめ問題が提示されているので、ゼミまでに個人で検討しておいて、講義時間のはじめの20分くらいでグループで話し合いをします。1グループ2問ほど発表するので、その問題についてさらに20分ほどグループ内で検討します。1グループ5分ほど発表し、その後は先生が解説します。
択一問題は6問出されるとのことですが、個人で検討するのは大変ではないですか?
1問1問はとても難しいという訳ではないので、すごく大変という訳ではないです。仮に分からなくても、グループで確認するので安心です。
後期には、自分が興味のある判例についてレポートの作成も行ったそうです。
また、夏季休業中に一度、一時間程度の夏期講習があったとのこと。
おわりに
各ゼミの成績評価方法と講義の流れについて、表にまとめてみました!
| 成績評価方法 | 講義の流れ | |
| 濱田ゼミ(刑法) | 判例報告+質疑応答+レポート(毎回) | 判例報告→ディスカッション |
| 美甘ゼミ(国際法) | レポート(テーマごと)+受講態度+期末レポート(後期) | 先生がテーマについて解説→グループで話し合い→全体へ発表 |
| 成澤ゼミ(憲法) | 事例問題の発表+質疑応答 | 事例問題の論点回答→先生の解説→質疑応答→先生の解説 |
| 宗村ゼミ(親族・相続法) | 受講態度等 | 問題について検討→発表→先生の解説 |
今回は4つのゼミについてインタビューを行いましたが、いかがだったでしょうか。
ゼミごとに講義の内容も進め方も全然違うので面白いですよね!
ゼミ選びの参考になれば嬉しいです!
最後まで読んでくださりありがとうございました!